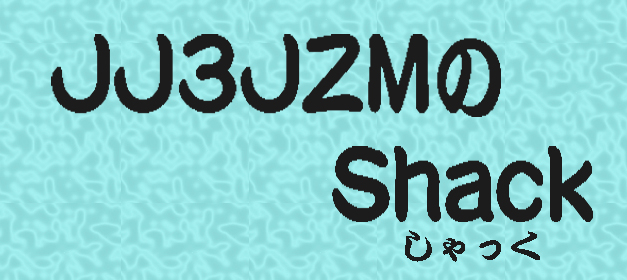
| JJ3JZMの所有する無線機(Rig)です。 自宅のアンテナはマルチバンドGP、使う都度、ポールを伸ばさなければならないこともあり、 滅多に出ません(HomeからのQSLは希少価値あり(^^;)) |
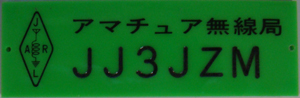 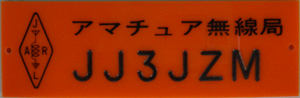 |
JARL会員のコールプレート。 入会するとJARL会員手帳とともに送られてきた。 資格ごとに色分けされ、1アマ:黄、2アマ:緑、電信級:白、電話級:茶色。 開局当時は電話級で茶色、その後一度再入会。 88年に無線を再開したとき、2アマで再々入会したため緑のプレートが送られてきた。 写真の茶色プレートは再入会したときのもので、最初の1枚は開局時に自宅に貼ったあと行方不明。 入会後上級資格を取得しても新しいプレートが送られて来る訳ではなく、従免のコピーを添えて、 別途費用を支払う必要があった。
一時、全て白に統一されていたが、色分けが復活、3アマ:青、4アマ:オレンジとなったが、 | ||
 |
FT−101Z 下段右 |
HF SSB/CW 100W ヒロ電子(北本市)がヤフオクに整備済みで出品していたものを落札、 さいたま市へ出かけるついでに、店に寄って引き取ってきた。 ラインナップには、周波数をデジタル表示するDタイプがあるが、 所有しているのはアナログ表示。 100W機だが50Wに低減すること条件に、移動局として保証認定を 受けている。 移動用電源がバッテリーにため、別途入手したDDコンを取り付けたが、 固定でテストしたあと、始めて移動に持ち出したときに故障。 修理に出してみたが部品が無く、修理不能で戻ってきており現在はShack に置かれたまま(;_;) |
|
FT−690 上段左下 |
6m ALL MODE 2.5W ヤフオクで落札。 ロッドアンテナを内蔵したポータブル機、単2電池8本使用。 外部電源端子はセンターマイナスのDCジャック。 本体下の専用リニア FL-6010(本体下)の電源も同じジャックを使ってい るが、こちらはセンタープラスとなぜか統一されていない。 付属のショルダーベルトは入手時既に失われていた。 | ||
MX−6S 上段右  |
6m SSB/CW 1W 通称ピコ6。 言わずと知れたミズホ通信を代表するシリーズで、初代は250mWだったが、これはその後に発売さ れた1W出力のSモデル。 キットで購入、メイン基板は組み立て調整済みだった。 電源投入直後、しばらくは周波数が安定せず、相手局はメインダイヤルで追跡しなければならない なほど変動することは有名。 CQに応答してきた相手の周波数が安定しないと思ったときは、大抵ピコ6を使っていると考えて 間違いない。 オプションの10Wリニア、CWサイドトーンユニットとともに専用ラック(幅12cm)に収納す ると、ちょっとした固定機(写真右)としても使える。 |
||
IC−7200M |
HF/6m SSB/AM/CW 50W 新製品には手を出さない主義だが、発売当初から気になっていたRigで、2009年ハムフェア会場で 購入。 もっとも50W機は在庫切れで、2日後、和歌山アイコムから直送されてきた。 フロントパネルはIC−756同様のテンキーが配置されているが、BAND切り替えが2アクション になっていたりと操作がかなり違っており、取説片手に30分ほどかけて初期設定を行い、やっと 使えるようになった。 MIC GainをMaxにしてもALCレベルを超えないところを見ると、IC−726のように変調が浅い のかと思ったのだがトークパワーは以前使っていたIC-706mk2GMより出ている様子。 |
||
FT−817 |
HF/6m/2m/430M ALL MODE 5W 発売された翌年、ハムフェア会場で購入。 2店舗で値段を聞いたところ、2店舗目のほうが高くかったので1店舗目の値段を言うと、そこま で下げると言うので購入。 (値段はよそで言わないでくれと口止めされたが) ハンディ機という位置づけらしいが、ポータブル機と言った方がしっくり来そうな大きさ。 HF〜430までALL BANDをカバーしており、かなり使い手のあるRigだと思う。 以前はmobileに仮置きし、移動の道中で聞いていたりしたが、mobileにIC-7100Mを取り付けて からは、使うことがすっかり減ってしまった。 | ||
IC−2N |
2m FM 1.5W 局長の所有期間が最も長いRigである。 1988年1月、秋葉原ラジオセンター2階の山本無線で購入。 販売開始は1980年でPLL 200ch、3桁サムホイールでのチャンネル選択など、当時から人気が高 く、後継機のはずのIC−02Nの方が先にカタログから消えるほどだった。 オプションのNi-Cdバッテリーパック(BP-5)に変えることで2.5Wまで出せる。 しかし、外部電源を繋ぐ端子が無く、バッテリーが果てたあとは乾電池専用となっている。 |
||
IC−W2 |
2m/430M FM 5W 430Mのハンディ機はIC−3Sを所有していたが、1000chをツマミで切り替えるのが結構大変 だったことで、テンキー付きDual Bandを購入。 5W出力だが、Finalの放熱をケース全体で行っているらしく、Hi-Powerで送信していると本体 が熱くなる。 また、熱暴走防止にためか、温度が上がるとPowerを低下させる設計で、1Wも出なくなるため、 通常はPowerをしぼって使用している。 (IC−3Sや固定機のIC−221も同じで当時のICOM共通の保護機能と思われる) | ||
IC−P3T |
430M FM 5W 94年ハムフェア会場で購入。 91年に発売されたとき、AI機能を搭載しているなど面白いものを出したなと思いながら店頭デモ を見ていた。 標準搭載されるNi-cdパックだとすっきりとした形になるが、乾電池ケースだと下に伸びる。 |
||
IC−12N |
1200M FM 1W ハムフェア特別局で1200Mを運用したことをきっかけに、1.2Gに出てみたくなりヤフオクで落札。 SQLが機能しない等難点ありとされていたが、QSOその他機能は支障が無い。 本体のみの出品で、付属アンテナは失われていた。 アンテナ端子がTNCで、取り付け可能なアンテナが市販されておらず、変換コネクタを探して 秋葉原を歩き回り、富士無線で買うことができた。 |
||
